今の時代は「多様性」の時代と言われ、ある意味で「飽和」の時代と言われています。
それは、食事においても、文化においても、職業においても、時代が進むことによって、ますます
多様化し、ますます豊かになっているということを意味します。
昔の日本と今の日本を比べてみましょう。
昔の大名が食べていたご馳走は、今の私たちは当然のように(そしてより安価で、安全に、おいしく)ありつけることができます。
職業や身分は「士農工商」という四つで定義されていた時代から、今は非常に多様化し、
このブログでも一つのテーマとしている「クリエイター」というそれまでとは全く新しい種類の生き方をする人も増えてきています。
文化も多様化し、音楽という文化の中からさらにジャンルの違い、音楽性の違いに留まらず精神性の違いからさらに多様化・細分化され、まさに無数の文化が誕生しているといえます。
現代のこの状況については誰も当然のように周知していることと思います。
ここで言いたいことは何か、というと
私たちは自己の欲求を満たしたり自己実現を果たすためのかつてないほど豊富な材料を手にしている、ということです。
より端的に言い換えると、私たちは今までにないほど自分自身の「これをしたい」「こうありたい」という(心理的・肉体的を問わない)欲求をいとも簡単に、素早く満たすことができるということです。
それは自体はとてもありがたいことといえます。
ですが、その一方でこの時代に生まれたからこその苦悩、いわば「欲求の苦悩」というのも、存在しうるといえるのではないでしょうか。
「ヘドニック・トレッドミル」という言葉をご存じでしょうか。
これは、ともすると私たちは決して満たされることのない欲求を永遠に求め続けるためにあてなく走り続けているものである。という考えを端的に言い表したものです(トレッドミル、というのはランキングマシーンのことです。ジムに通っている方ならご存じかと思いますが、壁を見つめながらトレッドミルの上を走っても壁にぶつかることは永遠にありません)。
私たちはあと少しで手が届くはずの幸せ─よりよい人間関係、より多くの収入、より多くの人脈など─を求めるためにつねに走り続けているようなものであるが、一度それらが手に入ると、それでは満たされなくなってしまうのです。
これに対する最大の解毒剤は、「もっと」を求めず、現状─いま、ここの状態で満たされている。幸せであるということ─を自覚するに尽きます。要するに仏教でいわれているところの「足るを知る」という状態を覚えることです。
しかし、これは、簡単に満ち足りることのできる現代では、推し量るに昔以上に難しい、現代人の最大の課題の一つとでもいえるのではないでしょうか。
食糧があるということ自体にだけ感謝することができた昔の人と違い、今の私たちはカツサンドの中の辛子の量が少し少なかっただけでも1時間は文句を言えそうです。
満たされやすくなったがために、却って少しのことで不満を持ってしまうようになるというのは皮肉なものですが、これは見方を変えれば「不満を持つ=沢山トレーニングをする機会がある」と前向きに捉えることができるかもしれません。
ぜひ、皆さんには不満のある状況、欲求が満たされていない状況というのを前向きに考えていただきたいのです。
・創造性は、常に「不完全さ」から生まれてくる
「足るを知る」こと、「限られた材料で何かをつくる」ことというのはこれをご覧のクリエイティブな皆さんにとっても非常に大切なスキルになります。
材料が限られている、選択肢が狭められている、ということは一見不自由でよくないことであると思われるかもしれませんが、創造性の観点から考えれば、むしろそういった「制約」こそ創造性、独創性の要であるといえるのです。
ホラー映画にA級映画が少ないのは、恐怖感をあおるシーンに迫力を持たせるための演出がワンパターンで陳腐化されやすいから、ということを聞いたことがあります。
とあるホラー映画では、その上さらに制作費用が限られているという「制約」があったにもかかわらず、それを生かしCGやメイク技術に頼らずそれまでなかった独自のカメラワークにより唯一無二の迫力と恐怖感を演出することができ、結果として超A級ホラー映画として上り詰めた作品が存在します。
不出の奇才、アルフレッド・ヒッチコックの映画でも白黒映画である、ということを活かし
チョコレートソースで血の描写を表現した、と言われています。
日本は多様な立地、気候から様々な農作物が取れます。
とうぜんながらある土地では収穫できない食べ物も別の土地ではとれたりします。
お米を育てられない地域では果物を育てることができるかもしれません。
そのように、ある意味制約的ともいえる条件を踏まえながら、その土地で一番適した食べ物を育てた結果、そのうちのいくつかが「特産物」として日本中の人に愛されているのです。
何かがない、という「制約」によってもたらされる創造性は、その不完全さを埋め合わせるだけではなく、さらにそれがあれば完全であっただろうと思われる状態さえも上回るほどのポテンシャルを常に秘めているといえるでしょう。

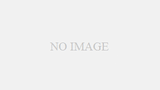
コメント