さて、今回は以前ご紹介した「数学力と創造性の関係」に関する記事の応用編となります。
以前の記事では、「学習経験によって得られる副次的な”気付き”の体験が創造性の源泉となる」というお話をしましたね。
そして、気付きを得られる手段としての数学の学習についてご紹介しました。
今回は、視点を変えて英語のような「語学学習」についても同様に創造性の観点から掘り下げていきたいと思います。
今回の記事は、前回の記事の続きとなっていますので、前回の記事を読んでいない方はぜひそちらを先にご参照くださいね。
・「サピア・ウォーフ仮説」から読み解く言語と創造力の関係
思考と言語の関係性を語る上で有名なのが「サピア・ウォーフ仮説」です。
これは言語学者のベンジャミン・ウォーフと人類学者のエドワード・サピアが提唱した仮説であり、
別名を「言語相対性理論」と呼ばれています。
これを簡単に説明すると、「異なる言語が異なる思考体系や世界観までもを形成する」という考えがベースとなっている理論のことです。
このベースの考えから、異なる言語を習得することが異なる思考や世界観を理解することに繋がり、それが発想力の拡大をもたらす、ということが言えます。
・「言葉のプロ」が持つ強大な創造力
言葉を仕事にする人、と聞くと「学校の先生」とか、「語学教師」のような、何かを教える立場にある人をいイメージするかもしれませんが、実際には「小説家」や「ラッパー」のような方も言葉のプロということができます。実はこういった「小説家」や「ラッパー」と呼ばれる方が語学力に富んだ人が多いというのをご存じでしょうか。
夏目 漱石や三島 由紀夫といった伝説的な小説家はさることながら、大学時代に英文科やフランス文学科を卒業してバイリンガル、トリリンガルとなっている方は非常に多いです。
ラッパーでも、shing02さんやVERBALさんといった方はアメリカの大学を卒業されておりバイリンガルとしてその実力をラップの世界でも発揮させています。
仮に帰国子女でないとしても、英語の発音が流暢な人が多いラッパーは数多いです。
そもそもがヒップホップ文化の本流がアメリカであることや、流暢なフローの為日本語の中に英語の歌詞を使用することが他の音楽ジャンルより必然的に多くなることから語学的関心が高くなることは容易に想像できます。
また、仮に小説家やラッパーの人がバイリンガルでなかったとして、それで創造性がないということは当然なく、言葉の持つ表現力を生かし新しい価値観を産み、人々の共感や感性を揺さぶるという点で高い創造性を発揮する必要があるということを付け加えておきます。
・多文化理解がもたらす創造性の種
大学で外国語を学んでこられた方はご存じかと思いますが、外国語学部という学部もあれば、中身は同じでも「言語文化学部」とか「欧米言語文化学部」といった名前の学部も存在します。
これは、言語と文化には密接な関係があり、言語を学ぶ上ではその言語が話されている国の文化の理解を必然的に理解する必要があるということを示唆しています。
そしてこれはこれまでのことを考えると(そして、このブログの記事をこれまで読んできた人なら)当然かもしれませんが、多文化理解が創造性を高めることに繋がります。
というのも、創造というものは体外にして異なる文化同士の結合によりもたらされるものだからです。
音楽の世界では、ヒップホップとJ-POPの融合やテクノとロックの融合などで独創的ながらも革新的な音楽を創出し一世を風靡した例があります。
料理の世界では、現在では浸透しているものも西洋の料理と東洋の料理を融合させることで生まれた奇跡の産物であったりします。
こういった文化×文化のバリエーションは、文化の数が多ければ多いほど増えていきます。
そして、特定の文化が融合して生まれた新しい文化もまた、別の文化と融合することによって新たな可能性を帯びる。このように終わることがなく、永久に、そして加速度的に増えていくわけです。
それはつまり、多言語習得による異文化理解は無限の発想力の源となる可能性を示唆しています。
発想力と柔軟な思考力が求められる企業の社長やビジネスリーダーの一部が英語だけでなく中国語といった異なる文化圏の言語を習得しているのは、そういった意味でも彼らの創造力を支える有益なバックアップとなっているということが言えるわけです。

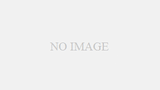
コメント