皆さんこんにちは、DeLTaです。
このブログでは、創造性をテーマの一つとして取り上げ、一人でも多くの人に創造性を生かした生活を送ってもらうための情報を提供しています。
今回は、一度原点に立ち返り、そもそも「なぜ創造性について考える必要があるか」についてお話していきます。
・「表現欲求」は、人間の根源的な欲求と結びついている
私たちは、何のために創造の活動をするのか?
それは、一つには「自己表現したい」という欲求があるからではないでしょうか。
(※このブログでは「自己表現欲求」という言葉を使用することがありますが、それは有名になりたい「自己承認欲求」とは別の欲求であると考えてください)
この「自己表現欲求」というのは、私たちの人類としての歴史をたどれば、その根強さを知ることができます。
ギリシアの時代には、賢人たちを崇めた彫刻が作られ、日本では和歌を通じて四季の移ろいを言葉にのせて表現する活動に情熱が注がれた時代もあったわけですよね。
現代では「食欲」「性欲」「睡眠欲」に加え、「自己承認欲求」という第四の欲求が発現しているという見方もありますが、私は新たに発言したというよりは、元来根源的に存在していた(けれども基本の三大欲求よりかは重要視されない)「自己表現欲求」が、現代のSNSに沿って再定義、カスタマイズされたものだと考えています。
要するに、現代のSNSで得られる承認欲求というのは、自分で表現したこと(=ツイート、写真、その他創作物)が他者に認められるという過程を通じて満たされる(承認してもらうという結果より先に自己表という行動が来る)ものという点で、承認欲求の原点(あるいは動機とでも言いましょうか)には自己表現が存在している、という風に私は考えています。
欲求というのは、それが満たされないと何かの形でそのエネルギーが滞留してしまい、いずれは健康に悪影響を及ぼすことも知られています。
食欲が満たされないと私たちは飢えてしまいますし、性欲が満たされないと不道徳な行為に走ってしまうことも考えられます。睡眠欲が満たされないとあらゆる病気の発症のリスクも高まってしまいます。
そして(これは他の記事でもお話していますが)、この「自己表現欲求」もまた、満たされないことで健康的な悪影響をもたらしてしまう可能性は十分にあるのです。
心理療法の一つに「箱庭療法」というものがあるのをご存じでしょうか。
これは、うつ病や自閉症といった精神面の病気に対して開発された方法に効果があるとされており、
特に再発率が高いといわれているうつ病において再発を予防する効果もあるといわれているのだそうです。
では具体的にどういったことをやるのか?薬によって治療するわけでも、師の説法をひたすらに聞くわけでもありません。
それは、ミニチュアの家の中にいろいろな玩具を置き、自身の内側にある深層心理を表現する
ことで、治療を行うというのです。
つまり、「自分自身を表現する」ことによって、病気を治すことが箱庭療法の本質といえるのではないでしょうか(もっとも私は心理の専門家ではありませんので、この点については断定的な表現は避けます)。
そしてそれは同時に、私たちが健康であるためにも何らかの創作を通じた自己表現をすることは理にかなっている、という見方ができるということです。
・必要性に迫られないからこそ、自分から踏み込まなければいけない。
精神科医であり、仏教徒として知られている名越康文さんの著書で、
人は実利によってではなく、マイナスを埋めようとするために行動する
ということが言われていました。
そういわれてみると、心当たりがある方もいらっしゃるかもしれません。
私たちは、「今より健康になりたい」というより、すでに何等かの悪影響が体に出ているときにはじめて食生活に気を付けよう、運動をしようという動機が強く生まれてくるものです。
お金を稼ごうという動機も、「お金持ちになって豊かな暮らしをしたい」と思うより、「こんな貧しいい生活から抜け出したい」という思いが強い時により一層行動力がわいてくるかもしれません。
要するに、私たちは「プラスアルファ」を得るための努力が強いモチベーションをもたらすわけではなく、「スティール・ボール・ラン」でジョニィ・ジョースターが言っていたように「マイナスをゼロに戻したい」という欲求を抱くときのほうが、結果として高いモチベーションを発揮することができるというのが、不都合な真実なのでしょう。
目の前にご馳走をぶら下げて走るよりも、熊が追っかけてくる状況から逃げる方が人は全力を出せるということなのです。
そうだとしたら─つまり、私たちが貧しくならないためにお金を稼ぎ、病気を悪化させたくないから摂生するとしたとき─創造性を求めるということの難しさは、それが「そうせざるを得ない」状況に陥ることがないということにあります。
今の時代は特に、創造性がなくても私たちは飢えたりお金に困ることはありません。
創造性があって得をすることがあるのは紛れもない事実ですが、学校は、そして社会は私たちに創造性を持つことの重要性を早い段階で切り捨ててくるものです。
だからこそ、このブログでは、皆さんに創造性について考えていただき、それぞれが自身の持つ創造力を発揮できるよう、そして少しでもその「必要性」を実感してもらえるよう情報を発信しているというわけです。
このブログでは、私が創造性に関する研究や書物などから調査した結果を私自身の哲学と照合・発展させながら皆さんにお伝えしていくことを一つの軸としています。
タイトルに【クリエイティブ講釈】と冒頭に題してあるものがそれにあたりますので、ぜひそのほかのブログ記事もご参照ください。
私自身、まだこのクリエイティブ理論の発展段階にいます。
このブログ(いずれ名前が変わる可能性はありますが)を「クリエイティブの樹」と題したのは、
私だけでなく、このブログに関与する皆さんと一緒に、まるで一つの樹を育てるように創造性について考えていきましょうという意味があります。
是非、私と一緒に、これからもクリエイティブの樹を育てていきましょう!

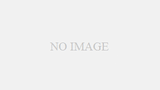
コメント