さて、今回の記事も前回、そして前々回の話の続きになります。
まだ読んでいない方は、まずはそちらを参考にしてみてください。
前々回、そして前回の内容を簡単に要約すると、
「人は不自由な状況、言い換えると“制約のある”状況でこそ創造性を発揮することができる」
「日常生活のあらゆる場面で、自分に制約を課し、それを楽しむことができる」
という内容でした。
今回は、おまけとしてこういった制約を自分自身に課す生活で得られるメリットを創造性以外の観点からお伝えします。
・「足るを知る」を体感的に学ぶことができる
「足るを知る」という言葉があるように
不満足な状態で満ち足りる練習というのは、古くから重要視されてきました。
ではどうしてそこまでして古くからそれが尊ばれてきたのでしょうか。
例えば仏教では、おそらく欲求には終わりがないという「ヘドニック・トレッドミル」の本質を理解しており、欲求をコントロールするための方法としての側面を持っていたのではないか、と考えています。
老子の言葉にも同様の表現があり、その場合は人格者として欲に溺れないことが優れたリーダーとなるうえで大切だということが協調されています。
文脈は若干異なりますが、西洋の偉人であるミルは、「満足な豚より不満足な人間」という言葉を残しています。
この言葉は、例えば一時的に得られる快楽(美味しいけど健康にはよくない食べ物を食べたり娯楽のために出費をすること)を先延ばしにしてより高次な喜び(食事を摂生して健康を楽しんだり貯金をして旅行に行くなど?)や自己実現を果たすことの重要性を表しています。
ここまで読んで、足るを知るという言葉が宗教や哲学上の文脈でしか使われていないことに嫌気が指した人のために別のお話をします
「マシュマロ・テスト」という有名なものがあります。
小さい子供を対象とした実験で、目の前のマシュマロを食べることを我慢できた子供ほどその後の人生における物質的な満足度(収入、人間関係の良好さ、健康度)が高いというデータがあるのです。
もっと端的に言えば、自制心を養えている人というのは、人生のあらゆる面でうまくいく可能性が高い、ということですね。

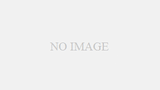
コメント