皆さんが学生の時、数学が一番できる人ってどんな感じでしたでしょうか?
これはよくきく話なのですが、数学が異常にできる人というのは、独特の世界観を有しているような人が多いのではないかと思います。
共感してもらえるかわかりませんが、皆さんの学校で、数学の先生というのは変わった人、ユニークな人が多かったのではないでしょうか。
これは単なる偶然ではない、というのがこのブログでの見解です。
Be aware(気づくこと)とTo know(知ること)の違い
学習を通じて得られる体験の一つに”気づき”というものがあります。
これは日常生活では得ようとしても得られないものの一つです。
以前、お仕事で一緒になった大学の先生が面白いことを言っていました。
「”知ること”と”気づくこと”は全く別のパラダイムである。AIの台頭で単純な知識の習得は意味をなさなくなったが、気づくという行為は人間の内側でのみ起こる。気づきはAIには代えられない」と。
つまり、一つ一つの知識(数式)の習得を通じてふと得られる高次元の気づき、シナプスとシナプスが結合する瞬間に広がる発想力。それこそAIがこれほど発達した時代においても英語や数学を学ぶ理由の一つではないのでしょうか。
もちろんこれは数学に限らず、世間で習い事といわれるほとんど全てのものに対し通用する話ではありますが、は特に、学問としての形式を帯びている点で気づきをもたらすプロセスが明確化されているといえるでしょう。
レオナルド・ダ・ヴィンチが学問の天才でありながら芸術にも才能がたけていた、というのは
芸術以外の学問(数学など)で得ていた気づきにより育まれた創造性を芸術に転用した、と考えるのが自然ではないでしょうか。
芸術大学の最難関である東京藝術大学には東大や医学部を蹴って入学する人がいると聞きます。
学問の最難関である東大や医学部に受かる頭脳だけでなく芸術センスも持ち合わせているとしたなら天性・天分は不平等と言いたくなるかもしれませんが、彼らの芸術センスもまた、5教科7科目という一般的な学問への勤勉な姿勢とそれによって得られる絶え間ない気づきの体験により培われた産物であるといえるかもしれません。
もしこのブログを読まれてる方が、数学が得意な方、あるいは数学を勉強することが好きであるとしたならば、是非その力を創造性という他の可能性に利用することができる、という一つの味方を信じて何か今まで自分がやってこなかった創造的な活動に生かしてみる、というのはいかがでしょうか。
そして、「数学なんて今まで大して勉強してこなかったし、これからもやりたい、とは思わないなあ、、」と思いの方、あえて今から数学の参考書を買って始める必要はありません。
先ほども言ったように、数学だけではなく、学習体験によって得られるアウェアネスこと0から1を生み出す創造性の源泉であることを思い出してください。
この認知的なアウェアネスを引き起こす体験というのは、その対象を無限に広げることができます。
例えば語学学習なんかでも同様の効果があります。語彙の引き出しが増えることでそれまで表現できなかったことを表現できるようになり、理解できなかったことが理解できるようになる。そのプロセスこそ「気づき」でしょう。
音楽が好きな人ならば、音楽理論を学んだり、実際に楽器を手足を用いて体験することによって、それまで聞くという一方的な対象であった音楽がより解像度の高いものとして理解できるようになります。
このブログの管理人である私自身は習い事として中国武術の教室に通っていますが、以前では意識することさえなかった体内の感覚に対する強い気づきを覚えるようになりました。中国武術は、特に体内の気の流れについて意識することが求められるのですが、練習の回数を重ねるごとに、少しその感覚をつかみかけてきています。
このように、学習対象は何であれ、学びを深め、それにより得られる気づきを重ねることが創造性を高めることにつながると思います。
今もしあなたが何かを学んでいて、それへ強い目的意識を持てなくなったときなどは、その学ぶという行為自体が価値ある行動なのだ、と考えてみてほしいのです。
このブログでは、創造性という漠然とした概念を最新の知見に基づき数値化、言語化することにより読者の方が少しでも創造性を有効活用し、自身の生活に取り入れることにより豊かな生活を営んでもらうことを試みの一つとしております。
今後も引き続きご期待ください。

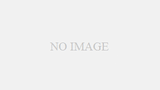
コメント