今回の記事は、前回お伝えした「制約」と「創造性」の関係について取り上げた記事の続きであり、応用編として書いたものです。
まだお読みになっていない方は、そちらをお読みください。
前回の記事では制約のある環境、すなわち何かを始めるのに十分といえる材料がそろっていないような環境下にいるときにこそ、人の持つ創造性の扉が開かれる、というお話をしました。
ここから一歩進んで、ではどのようにしてこの事実を日常生活にいかしていけばよいのかについて一緒に考えていきたいと思います。
落語家というと、あらかじめ定められた題目があり、それを表現方法を駆使して面白く聞かせることのできる人というのが、いわば技量の高い、テクニックのある人とみなされる、と思ってはいないでしょうか?
しかし、真の実力者は観客からのアドリブにも即興で答え、それを笑いに昇華させることができるものなのです。
実際、落語の世界では「三大噺」といい、異なる三人の観客からランダムにキーワードを一つづつ挙げてもらい、それらを一つの題目として話を即興でつくり人を笑わせるということができる人がいます。
これは日ごろからそういったトレーニングをしないと簡単になせる業ではありません。
事実、三大噺がつとまる人というのは落語の中でもリーダー格の存在のみらしいのです。
素人という立場に置かれている観客から与えられた話題で面白い話を作るというのは、まさに制約といえるわけですが、だからこそそれがうまくできた時にはとてつもない笑いとなり会場に還元されるというわけです。
とある玩具会社の開発担当の方が面白い話をしていました。それは新商品開発となるきっかけのアイディアを出す方法です。
それは「しりとり」だそうです。
気軽に、しりとりをして、適当にキーワードを上げていき、出てきたキーワードを組み合わせて一つの商品を作る、というものです。
例えば、「あ」から始まったとして、「あひる」→「ルーレット」→「トマト」と適当にキーワードを出していき、その上であひるとルーレットとトマトを組み合わせた商品を考えるのです。
これも三大噺と同じく、制約された条件で新しいものをつくるという意味でかなり難しい思考のトレーニングですが、確かにこれを行えば独創的な商品が作れることは間違いないでしょう(全く自由な、白紙の状態で何かを作れ、と言われてあひるとルーレットとトマトを組み合わせた商品を思いつく可能性がどこにあるでしょうか!)。
前回の記事でもお伝えした通り、制約という不自由がもたらす独創性は完全な自由に勝るポテンシャルを有しているのです。
次に、このように制約を課すトレーニングをどのように私たちのライフスタイルに組み込むかが問題になってきます。
色々な方法があると思います。
例えば「一日の食費を1000円以内にして満足のいく食事を作るにはどうしたらいいか?」と考えてみます。
まず、外食は選択肢から外れますね。そしてスーパーか専門店で特化のお肉を買うのもありです。
タンパク質で満腹感を出すために卵を買ったり、野菜を買うのもいいですね。パンよりお米の方がお腹も膨れます。
「市販のルーを使わないでスパイスでカレーを作る」もありでしょう。
家のお風呂で最高の気分を味わうにはどうすればよいか?と考えてみたとすれば、最初に思いつくのはよさげな入浴剤を買ったり、浴槽にアロマを焚くことを考えるかもしれません。
その次に防水のスピーカーで落ち着く音楽を流したり、観葉植物(造花でいいです)を置いてみること。CBDオイルで整ったり、照明の色を暖色から青にしたりとすると自宅の浴槽が特別な空間になります。
日々の生活で私たちはすでに時間や金銭的に全く自由という人は(私含め)少ないはずですから、その制約を創造性を活用する機会として多いに楽しむことが我々クリエイティブパーソンにとって肝要の精神といえるでしょう。
東京で100年近く続いている鉛筆会社があります。
シャープペンシルやボールペンが勉強道具や事務作業として普及し鉛筆の利用率が低下しつつある現代において、その会社は鉛筆をモチーフにしながら今なお新しいユニークな商品を開発している革新的な企業です。
その会長から話を伺った際に、大切にされている言葉がありました。
それは「無いものは、考えて作る」ということ。
「無い」という制約された状態から、考えることによって、新しいものを生み出すことが発想力の源になっているのだと痛感しました。
これだけ見ても、非常に多くの方が制約された状況を楽しみ、創造性を発揮する場として活かしているかがよくわかるのではないでしょうか。
そして、この「制約を楽しむ」という感覚を行動を通じて習慣化できるようになると思わぬ副産物を得られるようになるのです。
それについては、また次回お話したいと思います。

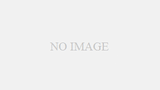
コメント